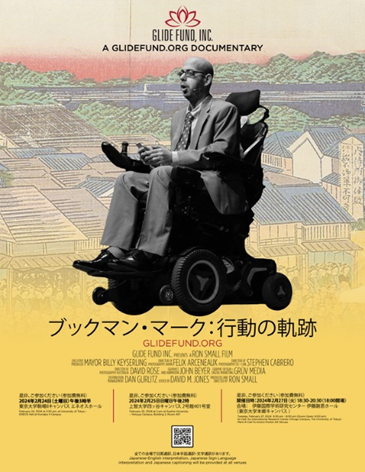田中恵美子
1. はじめに
2023年9月15日、樋口恵子さんが亡くなった。あの日からもう一年が経とうとしている。
私は9月13日に恵子さんにメールを送り、9月16日に電話で話そうと約束していた。その日は第20回障害学会(2023年9月16日、17日開催 於:東京大学)があって、私が書いた樋口恵子さんと近藤秀夫さんの本(田中2023)が先行販売されることになっていたからだ。「会場から電話する」と書いた私のメールに返信して、恵子さんは「本の発売にワクワクしている、その一方で、近藤さんが少し疲れ気味で電話に出るのを億劫がっている」と伝えてきた。本が手元に届いたら近藤さんもきっと喜んで電話に出てくれるだろう。そう思っていた。
それなのに。
私は、二度と恵子さんと話すことはできなかった。障害学会の会場からの電話には、お姉さんがでて、「恵子は昨日亡くなりました」とおっしゃった。それを聞いたときの気持ちは、でも忘れられない。人生にこんなことがあるのかと思った。
恵子さんの死因は、椅子から落ち、頭を打ってしまったことだったが、そのだいぶ前から肺が弱っていた。2018年に私がインタビューしたときの恵子さんの年齢は67歳だったが、肺が95歳だといわれたといっていた。2023年の5月には入院が長引き、「私の肺は限界のようです。病院のベッドの上では終わりたくない。誇りあるQOLを、自宅であなたのまとめてくれた本をだきしめて終わりたいと思います。ホントにありがとう」というメールが来て、びっくりし、四国に住む友人に連絡して会いに行ってもらったりした。そのころから“その日”を予感させ、ご自身も準備をしてきていた。しかし、、、それでもやっぱり急だった。
樋口恵子さんは、1980年代の日本の障害者自立生活運動における中心人物の一人であり、国際的にも活躍した一人である。今回は恵子さんの死を悼み、恵子さんの国際的な活躍とその影響について考察してみたいと思う。
2. 国際障害者年のころ―日本の障害福祉の国際化
恵子さんが海外との接点を持ち始めたのは、国際障害者年を契機としていた。恵子さんだけではない。多くの障害者運動のリーダーたちが、いや、日本の障害者施策そのものが海外との距離を縮めたのは国際障害者年のころだった。
1979年にはアメリカから自立生活運動の父と呼ばれるエド・ロバーツが来日し、講演を行った。そのころから徐々に国際化の波が押し寄せてきていた。1980年になると、近藤さんは車いすに乗った公務員として国際障害者年の国のイベントにも駆り出された。
恵子さんは、近藤さんの職場であった町田で非常勤職員として市の障害福祉事業に関わりながら、1981年にアメリカへのツアー旅行を企画し、日本からバークレーの街に障害者を連れていくという役割も果たした。その原動力は、先に挙げたエド・ロバーツの講演で受けた衝撃にあった。
「障害はパワーだ、エネルギーだ」 というエド・ロバーツの言葉に恵子さんは疑問しか浮かばなかったという。恵子さんにとって障害は仕方なく共に生きるしかないものだったからだ。
障害をどうして「パワー」や「エネルギー」などといえるのか?そんなふうに思える場所アメリカに、エドが働くCIL(Center for Independent Living 自立生活センター)に行ってみたい!!!
恵子さんのハートがググっと動いた瞬間だった。
1981年、ミスタードーナッツが日本で発売されて10年の記念すべき年に、国際障害者年と絡めたイベントが企画され、日本の障害者をアメリカに送る研修が始まった。これが今日まで続く『愛の輪基金』である。新聞に広告が載り、恵子さんもいつかこの研修に参加すると目標を立て、英会話の勉強を始め、コツコツと準備した。そして1984年、晴れて第4期生としてアメリカ・バークレーに旅立ったのであった。研修は半年間だったが、その後一度日本に帰国した後すぐにワシントンD.C.へと飛び、ジャスティン・ダートの下でインターンとして3か月働いた。
3. “障害”は社会にある
恵子さんはアメリカでデートに誘われたり、付き合ってほしいといわれたり、一人の“女性”として扱われた。この経験が自分を肯定する出来事だったと自著(樋口 1998)に記している。またアムトラックでの旅行を計画して受付の女性に障害者割引があるか尋ねたとき、「あなたは障害者ではないから」といわれ、驚いたこともあった。日本では、先ず障害者であって、人間として、ましてや性のある存在としてみられたこともなかった。それがアメリカという土地では同じ自分が人として、女性として認められる。こうした経験を通して、恵子さんは障害は社会にあることを実感していく。そして同じ経験をたくさんの人にしてほしいと、日本に戻ると、障害者旅行の企画をしては障害者を海外に連れて行った。
その中の一人に、千葉れい子さんがいる。彼女はのちに介助犬を日本に初めて紹介する人となるのだが、彼女が恵子さんと一緒に初めてアメリカのツアー旅行に行った時のことだ。彼女は日本でも電動車いすを利用していたが、この旅行ではアメリカで電動車いすを借りた。アメリカの電動車いすは日本の電動車いすに比べてスピードが速かった。乗りなれてくるとスイスイとツアーの旅行客の前に出てこられるようになった。いつもなら人の後ろについて歩き、時々は待ってもらわなくてはならないのに、この旅ではランチのレストランを探す際に、「私が見てくるわ~」と確認して戻ってきたりできる。旅の中でどんどん生き生きとしてくるれい子さんを見て、恵子さんは「道具一つでこんなに人が変わるのか」と実感した。れい子さんもまたこの旅で自分に自信をつけ、やがて自らのやりたいと思っていたことに、もちろん紆余曲折はあったが、進んでいったのだった。
恵子さんは海外旅行の意義をこんなふうに述べている。
「現状では、私達の社会は障害者にとってはなはだ住みにくい社会で、それはあたかも障害がすべての原因であるかのように言われているのだが、果たしてそうなのか。一定のアクセスが整った地域に、短期間でも身を置くことで見えてくるものがある。社会の側がつくった障壁(階段や利用できない公共交通機関など)とそれらが解決されて残るものが何なのかといったことを具体的に理解することができるのである」(樋口 1992)。
4. おわりに
恵子さんはその後、1989年にDPI女性障害者ネットワークを立ち上げ、優生保護法の改正に向けて運動を展開していく。1995年には中国・北京で行われた世界女性会議に出席し、女性運動と協同して分科会「優生保護法って何?」を開催し、そこで恵子さんは
「私は今、障害者として生きてこれてよかったと思います。障害を持って生きてきたことが、私をここまでひっぱり、育ててきたと思います。私にとって障害は私を構成する大切な個性です」
と「『私大好き』宣言」をするに至った。あの時のエド・ロバーツみたいに。
海外で過ごし、一人の人間として、一人の女性として受け止められた経験を通して、恵子さんの中で障害の意味が変わっていった。恵子さんは“障害”を、“社会にある障壁”“生きづらさ”としてとらえ、それを経験する者として健常の女性たちとも連帯し、社会を変えていこうとした。同時に広く世界の“障害”者運動ともつながっていった。もちろん国によって障害は異なる。だが差別や偏見を受けるという共通の経験をした者同士であるというシンパシーによってより強固につながることができたのではないだろうか。
国際障害者年という時代の波に乗ったことも確かである。しかしそれだけではない。現在の国際的な障害者運動の連帯への道が築かれた時代に恵子さんがいたことに大きな意味があったと思う。
文献
樋口恵子1998『エンジョイ自立生活-障害を最高の恵みとして』現代書館
樋口恵子1992「5 自立生活センターにおけるピア・カウンセリングの意義」『自立生活への鍵ーピア・カウンセリングの研究ー』ヒューマンケア協会:35-44
田中恵美子 2023 『障がいを恵みとして、社会を創る―近藤秀夫と樋口恵子』現代書館